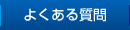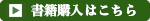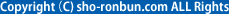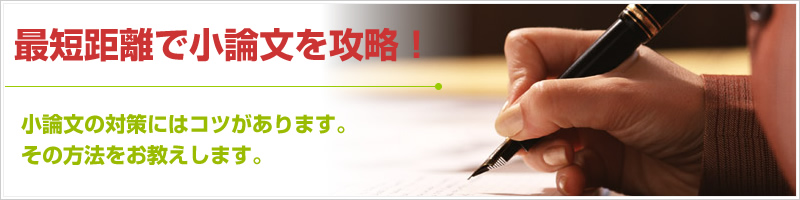
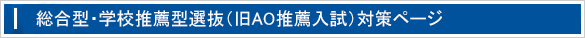
小論文.com HOME >総合型選抜・学校推薦型選抜対策
近年、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO推薦入試)を重視する大学がとても増加してきています。一般選抜よりも楽に大学入学を果たせるというような考えはもう通用しないようになってきています。倍率も総合型選抜の方が高いという大学・学部もあり、総合型選抜・学校推薦型選抜に関してもしっかりと対策をしておく必要があります。
総合型選抜・学校推薦型選抜に関しては、通常の小論文に必要な事項に加えて自己アピールという点がとても重要になってきます。総合型選抜・学校推薦型選抜において、志望理由書や自己推薦書、また面接やプレゼンにおいても、この「自己アピール」が合否を分ける大きな壁になっているといえるでしょう。
以下の特別講義にて総合型選抜・学校推薦型選抜対策の基本的な要素を学んだ上で、実際に小論文添削指導講座を受講し、インプットとアウトプットの両方を勉強することで万全の準備・対策をしていきましょう。
- はじめに
- 総合型選抜・学校推薦型選抜とは何か (1) 総合型選抜 (2) 学校推薦型選抜
- 総合型選抜・学校推薦型選抜を実施する大学が求める学生像
- 具体的な対策 (1) 志望理由書 (2) 自己推薦書 (3) 小論文 (4) 面接
- 受講生の声

1

小論文.comオリジナルテキスト「小論文の極意」でも書かれているように、小論文においてもっとも大切なことは論理的な文章を書くということです。論理的な文章を書いていくということは、客観的な証拠に基づいて証明をしていくということです。
ただ、今回みなさんが受験する総合型選抜・学校推薦型選抜は、自己アピールという主観的な要素も必要となってきます。これは小論文だけでなく、小論文と深く関係する「志望理由書」「自己推薦書」、また「面接」においても同様に必要です。
では、どのように客観的な証拠に基づいた論理的な文章と自己アピールという主観的な文章という相対する2要素を入れていけばよいのでしょうか。この点が総合型選抜・学校推薦型選抜に特有の難しさといえるでしょう。この総合型選抜・学校推薦型選抜に特有の要素をしっかり分析し学習していかなければ志望校合格が遠のいてしまいます。
そこでここから、総合型選抜・学校推薦型選抜に必要な、(1)志望理由書、(2)自己推薦書、(3)小論文、(4)面接で勝ち抜くために、客観的でかつ主観的な文章を論理的に書いていくという基礎的要素を学習していきます。総合型選抜・学校推薦型選抜の特徴をしっかりと分析し、その対策を学習していきましょう。そしてここで学習した知識をもとに総合型選抜・学校推薦型選抜対策の小論文、志望理由書、自己推薦書を書く訓練をし、添削指導されたことを元にそれらを練り直し続け、限りなく完璧なものに近づけていくことで、確実に志望校に合格できるようにがんばっていきましょう。総合型選抜・学校推薦型選抜ではこれら(1)志望理由書、(2)自己推薦書、(3)小論文、(4)面接が合否を分けるといっても過言ではありません。全力でがんばっていきましょう。
2

一般に推薦入試(選抜)といわれるものは、大きく分けて (1)総合型選抜、(2)学校推薦型選抜という2つに分けられます。この(1)、(2)のそれぞれについて、その特徴と対策を考えていきましょう。
(1) 総合型選抜 = 攻め重視
総合型選抜・学校推薦型選抜では、総合型選抜・学校推薦型選抜を実施する大学側によって入学者の受け入れ方針があらかじめ明示されていて、その大学に求められている学生像やその大学の教育方針が示されています。
ただここで、学校推薦型選抜が高校(高校長)の推薦が必要で、つまり現役受験生に限られることが多いのに対して、総合型選抜はそのような推薦は必要なく、自己推薦のみで受験できるため、現役に限らず浪人生でも総合型選抜を受験できるのが特徴です。
一般に、子どもの数が減少しているのに対し大学数が増加している現状のため、大学は生き残りをかけて通常の1月~3月の一般受験を待たずに先に優秀な学生を確保しようと、この総合型選抜がどんどん広がってきています。
この総合型選抜は、(2)の学校推薦型選抜とは違い、大学側が高校を信用してあらかじめ出願枠を割り振っているわけではないため、「ほとんど合格したも同然」などということはまったくなく、学校推薦型選抜のように簡単には合格できません。また最近の総合型選抜(旧AO入試)では、特に国公立大学や難関私立大学などで小論文だけでなく数学的要素や理科的要素も含んだ総合問題が課されたり、また慶應義塾大学SFC(総合政策学部・環境情報学部)などでは自分らしいオリジナルの活動の様子(ボランティアなど)が要求されたりもします。
すなわち、総合型選抜で私たちがすべきことは、「守り」の文章を書くというよりもある程度「攻め」の文章を書くということです。大学が求めている学生像や教育方針をしっかりと理解し、その中で自分らしさを存分に表現し、他の受験生とは違うんだというところを強くアピールしていく必要があります。(2)の学校推薦型選抜とは違い、高校自体の信用で受験させてもらっているというわけではなく、自分自身の力で勝負し、自分自身を輝かせることで他の受験生に打ち勝つ必要があります。
(2) 学校推薦型選抜 = 守り重視
学校推薦型選抜というのは、推薦をする大学側が特定の高校に対して出願枠を割り振るという入試方法で、高校での評価(通知簿等)を元にして合否が決まります。この入試方法は専願制で現役受験生のみが出願できるもので、高校の推薦さえあればその時点でほとんど合格したも同然ということになります。これは、大学側がその受験生個人というよりも、その高校自体を信用しているからこそ推薦出願枠を割り振っているわけで、その受験生自体にはあまり大きなウェイトがかかっていないためです。このようなことから、大きなミスをしない限りは不合格になるということはないと考えておいた方が良いでしょう。
すなわち、学校推薦型選抜で私たちがすべきことは、「攻め」の文章を書くというよりも「守り」の文章を書くということです。もうすでに高校自体を信用しているわけですから、悪く言えば余計なことをしなければ大丈夫というわけです。したがって学校推薦型選抜では、あまり強い過激な主観を出すよりも、一般論に近い無難な文章を書いていく必要があります。
3

これまで大学入試はいわゆる一般選抜が主流でした。なんといっても客観的に学力を判定できますし、何より大学側の手間がかかりません。にもかかわらず大学はなぜオープンキャンパスや大学説明会など手間をかけてまで総合型選抜・学校推薦型選抜を実施するのでしょうか。
それは、先ほど記述しましたように、子どもの数と大学の数の関係もありますが、客観的な学力検査だけで合否を判定していると勉強はできるが人間性に欠けるといった学生が多くなってしまい、大学が求める自発的に勉強し、学問だけでなく社会に役に立つ人間がいなくなってしまったからだといえるでしょう。そこで総合型選抜・学校推薦型選抜を通して、時間や手間をかけてでも何より「人間性」を判定しているということです。もちろん英語や数学、国語といった基礎的な学力を有していることも前提として大切ですが、それだけでなくさらに「自分が何をやりたいのか、そのために何をしたいのか」といったような「人間性」を有していることがとても大切なのです。ではその①基礎学力と②人間性の2要素を検査するのに最適なのは何でしょうか。それこそが小論文であり志望理由書であり自己推薦書であるわけです。小論文には、英語や数学、国語に必要な「論理力」が欠かせませんし、課題になる時事問題・社会問題などに対する考え方には「人間性」が必要となってきます。
このように総合型選抜・学校推薦型選抜では、志望理由書、自己推薦書、小論文がとても重要なのです。
4

それでは上記2と3を踏まえた上で、具体的に総合型選抜・学校推薦型選抜対策の【1】志望理由書、【2】自己推薦書、【3】小論文、【4】面接の対策法を考えていきましょう。

ここまでのことから、総合型選抜・学校推薦型選抜を課す大学が求める学生像は、基礎学力+人間性を兼ね備えた学生であるといえます。基礎学力というのは他の受験生と比べて大きく差が出るものではありませんから、人間性という部分が総合型選抜・学校推薦型選抜ではもっとも重要であるともいえるでしょう。そのように考えると、この志望理由書という書類がこの総合型選抜・学校推薦型選抜でもっとも大切な合否を左右する書類であると言っても言い過ぎではないでしょう。またこの志望理由書は、次から考えていく【2】自己推薦書、【3】小論文、そして【4】面接とも連携して、話の筋にブレがないように作成していく必要があります。論理性が少しでも崩れてしまうとたちまち合格が遠ざかってしまいます。このように、この志望理由書は、自己推薦書、小論文、面接にも大いに影響してきますから、総合型選抜・学校推薦型選抜の根幹に関わる書類だということがいえます。じっくりと吟味して論理的な文章を作っていきましょう。
では具体的に志望理由書はどのように書いていけば良いのでしょうか。これには、「小論文の極意」で書かれているような通常の小論文の要素に何を加えておく必要があるのかということを考えておかなければなりません。それは書き手の人生の①過去②現在③将来の3要素です。
基本的に小論文というのは、①仮説、②論理展開、③結論の3部で構成していきます。課題に対しての自分の意見を1つアピールしていきます。その1つの意見を①仮説の段落に端的に表現していきます。そしてその1つのことに対して、なぜそのように考えるのかについて対比や例示のようなテクニックを用いて論理的に説明をしていくわけです。それが②論理展開の段落ですね。そしてこれらの論理をまとめるのが③結論の段落です。
志望理由書もこれと同じように①仮説、②論理展開、③結論の3部で構成していきます。その流れも通常の小論文とまったく同じです。ただし、志望理由書は書く流れがほぼ1つに決まっているといえます。それが①過去②現在③将来の3要素です。
志望理由書というのは基本的に、志望する大学に入っていったい何をしていきたいのかという③将来の要素を書くのが基本であり、それが目的です。ですから、①仮説の段落、及び最終的な③結論の段落には、この「将来=大学で何をしたいのか」ということについて書いていく必要があります。そして②論理展開の段落に、なぜこの大学を選択したのかという根拠を論理的に説明をしていくわけですね。では「なぜその大学を選択することになるのか」という根拠はどこにあると思いますか。それはもちろん、その人のこれまでの人生、つまりその人の①過去にあるでしょう。例えば、過去に大きなケガをして入院をした際に命の大切さを学んだことで医師を目指すことにしたり、過去に見たテレビ番組で海外の貧困な国々の人々を見てボランティアをするためにまずは英語を学ぼうとしたり、というようなことですね。何らかの要因が過去から現在に向けてあり、だからこそその目標のために大学を目指しているということです。そして、②現在の自分がいかにその大学に適しているのか、またどれだけその夢を今も思い続けているのかという現在の自己分析が必要です。
つまり、志望理由書は下図のような構成にしていくべきだといえます。
① 仮説の段落 【将来】←大学に入って何をしたいのか
② 論理展開の段落
<1>【過去】:エピソード・経験・出会い
<2>【現在】:自分の能力、長所・短所
<3>【将来】:<1><2>から帰結
③ 結論の段落 【将来】←②論理展開の段落を踏まえて、だからこそ大学で何をしたいのか
このように志望理由書では基本的に①過去、②現在があって③将来があるというように時系列に並ぶものです。ただ、実際にみなさんはそのような時系列にすぐに並べられるでしょうか。実際にはなかなか難しいことでしょう。なぜなら、先ほどの例のような明らかな経験があるわけでもなく、なぜかわからないし漠然としているけれど将来こうなりたいとか、はたまた将来どうなりたいとかもまだわからないけれど、でもなんとなくこの大学には行きたいんだ、といったような人も少なくないはずです。確かに図のようにビビビと来るような経験があって、だからこその現在・将来だという論理がクリアにあれば良いのですが、実際にはなかなかそうもいかないものでしょう。むしろそのような受験生の方が多いかもしれません。
そこで必要な作業が「落とし込み」です。本来は①過去②現在③将来という順番で論理があるはずなのですが、今明らかなのは③将来どうしたいのかということだけだとすると、頭の中の思考順序として、③将来→①過去②現在、と「逆算=落とし込み」をしていくわけです。ある意味、無理やり根拠を作っていくということですね。将来の漠然とした目標に対して根拠付けをしていくわけですね。そのためにも、その漠然とした将来の目標をしっかりと分析をし、その目標に対する現在あるべき姿、過去のあるべき姿を逆算していきましょう。
人それぞれにそれぞれの人生がありますから、この「落とし込み」はやはり1人1人で大きく違います。これは小論文添削講座の中で担当講師からヒアリングを求められますので、その中で自分自身を深く分析し、論理的な説得力のある志望理由書を一緒に作りあげていきましょう。大学が求める学生像と自分の将来に対する考え方についてしっかりと分析・吟味し照合していくことで、世界で1つの立派な志望理由書を作成しましょう。この落とし込み作業は、大学受験だけでなくこれからの人生を歩んでいく上で、きっと大きな財産になるはずです。

大学によってはこの自己推薦書の提出が必要な場合と不要な場合があります。志望理由書とどうしても内容が似てきますから、自己推薦書を志望理由書に含めるということで提出を不要とする大学もあるようです。
ここでは自己推薦書の提出が必要な場合について考えます。先ほども述べましたように、自己推薦書というのはどうしても志望理由書と内容が似てきてしまいます。しかし、もし同じような内容のものを書くのであれば、志望理由書と自己推薦書の2つを別のものとして提出するように要求する大学側の期待に応えていないことになってしまいます。大学側が別の意味がある書類だと認識している以上、同内容のものを書いてはいけません。
では、志望理由書と自己推薦書をどのように区別するのかということが大切になってきます。上記【1】の「志望理由書」では、①過去②現在③将来の論理が大切だと説明いたしました。ただ、「志望理由書」つまりなぜこの大学を志望するのかを書く書類なわけですから、③将来に何をしたいのかというのがメインテーマとなります。大学に入ってどのような勉強がしたいのか、またさらに卒業後どのような人間になりたいのかということについて論じていくわけです。それに対して「自己推薦書」は今の自分を自分自身で推薦する書類なわけですから、②現在の自分の姿とその現在に至るまでの①過去の自分についてというのがメインテーマとなります。将来の自分はまだ未定事項ですから、この書類には書くことはできません。現在までの自分についてしっかりと客観的に自己分析をし、アピールをしていくということです。
このようにして志望理由書と自己推薦書の住み分けをすることで、志望理由書と自己推薦書を別の書類として作成していきましょう。こちらも小論文添削講座の中で世界で1つの自己推薦書を作成していきましょう。

小論文については、基本的には学習冊子【小論文の極意】に書かれているような通常通りの作業を進めていきましょう。ただ、推薦型選抜という入試形態では「①基礎学力+②人間性」が問われているわけですから、通常の小論文に必要な「論理=①基礎学力」に加えて、「自己アピール=②人間性」についてもしっかりと表現しておく必要があります。

面接は受験生の人間性の最終確認として実施されるものです。ということは「志望理由書」に書いたすべての事項、つまり「①過去②現在③将来の自分像=自分の人間性」を最終確認するということです。すなわち、面接対策として最も大切なことは志望理由書をしっかりと作り上げ、それを自分の中でしっかりと再確認をするということです。
上記【1】志望理由書、【2】自己推薦書、【3】小論文は、究極で考えると別の人に書いてもらってそれを提出することもできます。しかしその最終確認である【4】面接は他の誰にもできません。受験生本人にしかできないわけです。
だからこそ、小論文ドットコムでは、【1】志望理由書、【2】自己推薦書、【3】小論文を私どもの専任講師が作成するというようなことは絶対に致しません。小論文ドットコムの最終目的は、受講生が志望校に合格することです。そのためには、受験生本人でしかできない【4】面接での成功も不可欠です。【1】志望理由書、【2】自己推薦書、【3】小論文を受講生自らで自分の人生について一生懸命に思考し吟味し、十分に試行錯誤していただいた上で、私どものお手伝いを参考にしていただきながら“自らの力で”作成していただきたいのです。面接ではその試行錯誤が大きな力となってくれるはずです。
この【4】面接というのは、試験官と面と向かっての試験ですから、小手先の対策は通用しません。志望理由書を時間をかけて“自らの力で”作成することで、自分の人生に1つの筋を通し、自分の中で納得した上で面接試験に臨むべきでしょう。すなわち、面接対策として最も大切なことは志望理由書をしっかりと作成することだといえます。
ただ、面接というのは人と人との対話ですからどうしても緊張してしまい、いつもの自分らしさが出ないのではないかと心配される方も多いでしょう。しかし、他の受験生はもっともっと緊張しているはずです。というのも、他の受講生はみなさんのように、こうやってしっかりとAO・推薦入試対策をやっていないものです。みなさんはただただ、小論文添削講座で一緒に作り上げた志望理由書や自己推薦書などをしっかりと確認し、面接でどのようなことをアピールするのかを再確認しておけば良いのです。やるべきことは明白ですから、例え緊張したとしても話すべき内容をしっかり伝えることさえできれば何ら問題はありません。緊張して顔から汗をかいている方がむしろ、試験官からは「まじめそうな良さそうな人だ」と好印象を与えられるかもしれません。
また、まれにその緊張をさらに増幅させるような突拍子もない質問が来たりもします。例えば「うちの大学があなたを合格させるメリットは何ですか」というような質問が来るかもしれません。一瞬、頭が真っ白になってしまうかもしれませんが、あまり深く考えないようにしてください。面接というのは、その人の「人間性」を見ているわけであって、実際にどのようなメリット・デメリットがあるのかを分析したいわけではありません。表面上、質問の仕方が多少変わっていたとしても、聞かれているのは「人間性」ですから、自己アピールをどんどんしていけばいいんだ、と考えておきましょう。ミクロ的な解答ではなく、マクロ的な大きな視点での解答をしていくようにしていきましょう。
これまでのように、あくまでも面接は「人間性」を見ているわけですから、答えることを前日に暗記していったり、参考書のままの答えを用意したり、といったような小手先の対策は逆効果になります。自分の良いところをアピールするんだという大きな視点での再確認をしておきましょう。
5

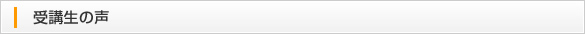
わたしは、学校推薦型選抜で小論文が必要だったのですが、試験2週間前までは学校の先生に少し添削してもらうだけでした。でも、試験の日がだんだん近づくにつれてどんどん不安になってしまいました。もう2週間前だからダメで元々だという気持ちで小論文に関するサイトを探していたところ、小論文.comを見つけました。
他のサイトや講座も調べてみたのですが、返却には最短でも3、4日かかると書かれているものばかりだったので、入試2週間前の私にとっては中途半端に終わってしまって何も意味がなくなると思っていたのですが、小論文.comを見つけて、翌朝返却コースなら9時間以内で返却されると書かれてあったので、すぐに翌朝返却コースを申し込みました。すると、1回目は夜に書いてメールに添付して送ったのですが、翌日の朝9時にメールを見るともう添削済みの原稿が返却されていました。それでその解説を見て、またその日の夜に書いて送ってみると、翌朝にはまた返却されてきていました。翌朝返却コースの返却の速さにはびっくりです。入試2週間前でもう半分あきらめかけていたので、すごく助かりました。入試までの2週間は、小論文.comでの勉強に明け暮れました。とても勇気付けられるアドバイスもいただいてうれしかったです。また、「小論文の極意」には、あいまいな感じがする小論文試験の対策が明確に書かれてあって、「小論文の極意」の通りに行動するだけでよかったのでとても助かりました。
「小論文の極意」を読むだけでもとても勉強になったと思います。実質入試2週間前から小論文の勉強を始めたようなものですが、小論文.comにお世話になったこの2週間ですごく伸びたと思います。
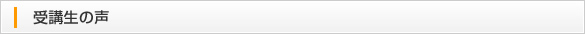
私は総合型選抜(小論文と面接)でこの大学に合格しました。私はとにかく「小論文」というものを書くのが苦手でした。高校で受けていた小論文模試の結果は、全国平均よりいつも低かったのです。
しかも、私がこの小論文.comに申し込んだのは、もう試験の1ヶ月前でした。ですが、きっと集中してやれば出来る!と信じて申し込みました。添削して返ってきた答案には、わかりやすく、簡潔に説明が書かれていました。
私は次の課題をこなす前、その説明を思い出して書くようにしました。また、小論文を書く前に、小論文.com独自の答案マップを毎回書くようにしていました。その結果、私は以前よりはるかにうまく、かつ「早く」書くことが出来るようになり
ました。この「早く」書けるようになったのは答案マップのおかげだと思います。
実際の試験では、800字を60分以内に書くというものでしたが、私は9割以上埋めて、約35分で書き上げてしまうことが出来ました。また、この試験の前にあった2回の小論文模試では、全国平均よりも上の点数を取ることが出来ました。以前はE判定だったのがB判定まで上げることが出来ました。とにかく、本番では自信がつき、落ち着いて書くことが出来たのが良かったです。小論文が苦手な方でも、小論文.comを信じて最後までやれば、誰でもうまく、早く書けるようになると思います。
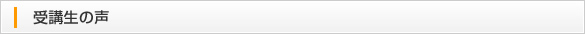
私は、総合型選抜・学校推薦型選抜での大学受験でした。科目は小論文と面接でした。
推薦型選抜関係でインターネットで検索していたところ小論文.comを見つけました。まずは小論文の極意を読んで、それから専用ページの対策を読みました。納得のできる理論で説明が書かれていたので、これは信用できるなと思い申し込みました。まずは基礎完成コースを受講し、教材持込コースと書類完成コース・面接回答コースは並行して受講しました。
書類完成コース・面接回答コースでは何度も質問、提出を繰り返して、練って練って練ったものを作り上げました。推薦型選抜では志望理由書や面接はとても大切だと何度も言われていたので私も一生懸命がんばりました。
おかげで入試には見事合格しました。色々助けてもらったので、何が効果があったのかはわからないくらいですが、私の個人的な感想としては、先生とのメールのやり取りの中で大きく勇気付けられたのが一番だったと思います。もちろん添削自体もよかったのですが、それ以外のケアに助けられた気がします。本当にありがとうございました。
続けて【受講生の声】で、実際に合格されている先輩方が添削者とどのように協力をして最短距離で合格できているのかを見てみましょう。
また【小論文.comの考え方】でより具体的な対策方法をご確認ください。